こんにちは、もちです。
知人に勧められて読んだ、『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』。
紙の本を手にするとわかるそこそこの分厚さ(約440ページ)ですが、読んでみるとなかなか面白いことが書かれています。
これからの時代を生きる老若男女すべての人にとっての必読書になると思います。
とはいえ、上述の分厚さがハードルを格段に上げていることもあり、読みたくてもなかなか手に取れていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「そんなに分厚いのいきなり読む気になれない」「読む前にさわりだけでも知りたい」という方のために、簡単に『シン・ニホン』の要約や感想などをまとめました。
読む前の参考にしていただければと思います。
『シン・ニホン』を一言で表すと
まず、この『シン・ニホン』を一言で表すとしたら、
「これからの時代を生きるための処方箋」であると私は考えます。
もちろん、こんな約440ページにもわたる処方箋なんて普通はありませんが(笑)
でもそれくらい、今の日本の課題をどう解決していくかのエッセンスが詰め込まれています。
現代日本の停滞感と真正面から向き合う
著者の安宅さんもおっしゃる通り、現在の日本には停滞感に根差した悲観論・根拠のない楽観論などが渦巻くカオスな状況です。
高齢化する社会、年金2000万円問題、貧困問題・・・挙げるとキリがありません。
そんな危機に対して、意味のない煽りや悲観、半ば目を背けるような楽観はやめて、問題と真っ向から向き合おうというのが本書の趣旨です。
著者の安宅和人さんってどんな人?
著者の安宅和人(あたか・かずと)さんってどんな方なんでしょうか?
安宅さんは東京大学の大学院を卒業後、マッキンゼーに入社。
その後イェール大学に留学し、PhD(Doctor of Philosophy, 博士号)を取得しました。
そして2008年には現職のヤフーに入社。
本書のサブタイトルにもなっている「データ」や「AI」だけでなく、分野横断的な事業開発に携わっていらっしゃるようです。
さらには内閣府のイノベーション会議でも委員を務められているということで、まさにマルチな活躍をされている方ですね。
『イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」』という、出版から10年以上経った今も書店の目立つところに置かれるような名著も書かれています。
次は実際に、本書で取り上げられているトピックの重要な部分について、かいつまんで要約していきます。
データ×AIの世界は、指数関数的に変化をとげる
日々暮らしていても私たちは実感しづらいかもしれませんが、データ×AIが一般的となる世界では、変化が指数関数的に起こることになると著者はいいます。
指数関数がピンと来ない方は、とにかく劇的で、桁が変わっていくようなイメージを持ってみてください。
安宅さんは本書の冒頭で囲碁の世界での対AI戦の話題を挙げていますが、囲碁が生まれて約2000年のうち、機械学習が行われるようになってからたった4年でトッププロが誰も勝てない状況になりました。
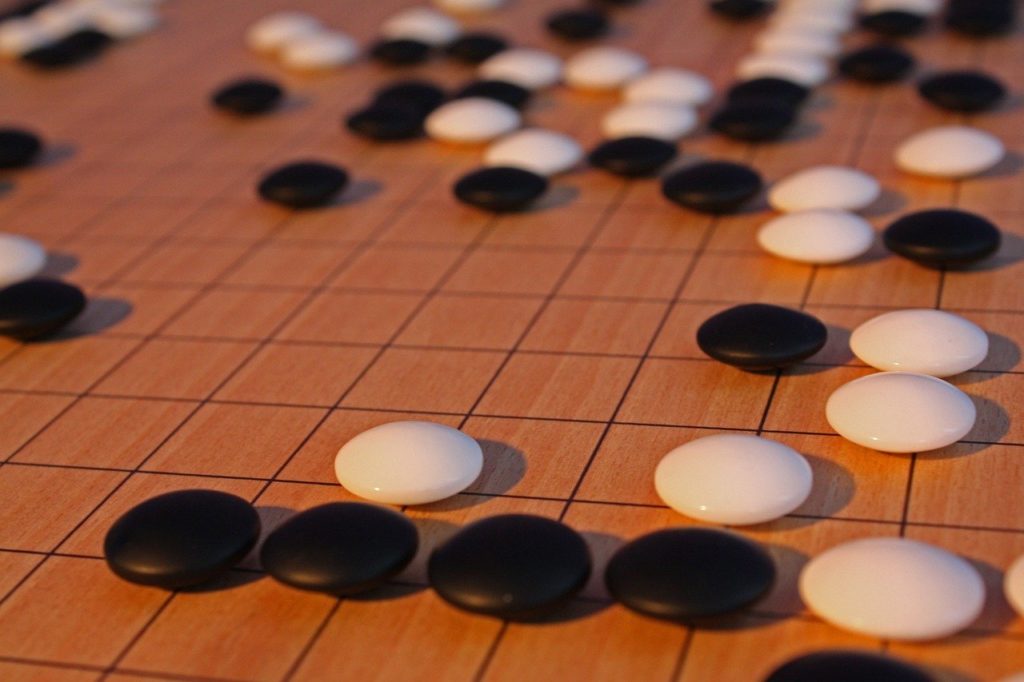
そのくらい速くめまぐるしい変化が起こることを前提に思考しなければなりません。
例外となる産業はあるのか?
昨今、あらゆる業界がデータ×AI化の煽りを受けていますが、この影響を受けないような例外はあるのでしょうか。
安宅さんの主張としては、「例外はない」とのことです。
テクノロジーの浸透しづらい繊維・アパレルや小売業界、さらには農業までもこのデータ×AI化の影響をすでに受けており、どの業界にいてもこの流れに逆らうことはできません。
そのため、「自分の職業には関係ないかも」と思っていた人も油断できないのです。
収益構造が二重に
また、データ×AIの世界では商品やサービスに「完成」がなくなると筆者は指摘します。
商品やサービスの販売後も、使用データは常にインターネットを通じてクラウド上に転送され、改善や進化が続くからです。
本書の中で安宅さんはソニーの犬型ロボットaibo(アイボ)を具体的に挙げています。
2018年に発売されたaiboには月々のサブスクリプションのプランが設定されており、データを吸い上げてはフィードバックして、aiboが成長していきます。
企業側にとっては継続的な収益やそれに伴う安定性を獲得するチャンスが大きくなった時代ですね。
日本のデータ×AI化の現状
実際に日本でデータ×AIを取り巻く状況とはどうなっているのでしょうか。
結論から言うと、日本は大きく後れを取っているのが現状です。
まずは検索エンジン。
私たちが使うものとしてはGoogleが一般的ですよね。
日本ではヤフーという独自の検索エンジンがありますが、使っている人は周りでもそんなに多くない印象です。
他にも、日本のコマースの分野では楽天市場がありますが、規模ではAmazonに全く勝てていない状態ですよね。
このような状況は両社が取得できるデータ量にも直結していて、安宅さんの言葉を借りるなら「データ量と空間づくりで土俵に立てていない」ようなものです。
SNSにおいても、LINEとWhatsApp, WeChatではユーザー数・データ量ともに桁の違いがあります。
また、空間づくりという面でも日本は厳しい状況。
たとえば自動運転の分野では、日本には自動走行に適した道が少なすぎるということも問題になっています。
これがデータ利活用へのハードルを高いものにしています。
教育構造にも問題点が
また、日本にはデータ×AIのエンジニアや専門家が少ないこと、ひいては理数素養のある人間が育っていかない教育構造にも問題があると筆者は指摘します。
ただ単に理系の学生が少ないことが原因ではなく、文系か理系かに関係なくすべての人が学ぶべき理数素養が、文系学生の多くに教えられていないというものです。
他にも、海外と比べてPhD(博士、つまり研究開発をリードする人材)の数が圧倒的に少ないことも深刻な問題となっています。
日本では博士課程に進む人や研究者を支援する制度や予算が十分とはいえず、その経済状況の厳しさもPhDを少なくしている原因であるといいます。
ノーベル賞を取った日本人受賞者が、実は海外で研究していたというニュースを耳にしたことのある方も多いでしょう。
これは日本の厳しい現状を反映しているのです。
脱「選択と集中」
それでは、日本はこれらの課題をどう克服していくべきなのでしょうか。
安宅さんは、脱「選択と集中」を行う必要があると主張しています。
「選択と集中」とは、特定の業界・分野にリソースを集中投下し、効率やパフォーマンスを上げていくことを指し、1990年代ごろから使われるようになりました。
しかし国の科学技術予算においては、その額の大きさが直接的に競争力につながるため、安易な切り捨ては国力の低下を招きます。
むしろ真逆で、幅広い分野に予算を回すべきであると筆者は指摘します。
イニシアチブ・ポートフォリオを作る
国の予算については上記の考え方で対処するとして、企業やそれに属する個人レベルでは、未来に向けてどのような意識改革を行えば良いのでしょうか。
これに関しては、マッキンゼーで考案された「イニシアチブ・ポートフォリオ」の作成を安宅さんは推奨しています。
イニシアチブ・ポートフォリオとは、事業や取り組みを「社会への馴染みやすさ」と「効果実現のタイミング」の2軸のマトリクスの中に配置する方法です。
主な事業を配置したマトリクスを俯瞰することで、短期的な結果を追い求める方向に行きすぎていないか、あるいはリスクを避けすぎていないかをチェックすることができます。
著者がめざす未来「風の谷」とは?
そして、本書の最後で著者は理想の日本づくりとして「風の谷」という構想を掲げています。
「風の谷」と聞いて「急にナウシカの話?」と思ったかもしれませんが、まさにこの「風の谷」は「風の谷のナウシカ」から着想を得ています。
風の谷のナウシカといえば、地球の表面は人類にとって猛毒の腐海(ふかい)に覆われ、人間たちは限られた場所「風の谷」で暮らしているという設定。
これと同じこと、つまり最新のテクノロジーを駆使しながら、地方などの自然の残っている土地を住みやすい場所へとクリエイトしていくというのが風の谷の構想です。
これを「都市集中型の未来へのオルタナティブ」と安宅さんは表現しています。
僕らはどんな未来を残すつもりなのか。
本書6章「残すに値する未来」より
それが今、一人ひとりに問われている。
そんな言葉を残して、本書は締めくくられています。
読んでいるだけで「こいつやるな」と思わせる名著
改めて、この本は良書だったと思います。
内容が上っ面だけではなくて、正面から日本の課題に切り込んだ一冊でした。
正直、周りにも「シン・ニホン読みました!」と言うだけで、賢い人には「こいつやるな」と思われるんじゃないでしょうか(笑)
ちょっと前で言う「『ホモ・デウス』を読んでいた人」並みのインパクトがあると思います。
ただし今回ここで紹介したのはあくまで上澄みです。
ちゃんと理解するためには自分で読むのが一番ですし、内容が濃すぎてここに書ききれなかったこともたくさんあります。
この記事を読んだだけの「知ったかぶり」で恥をかかないように注意してくださいね。
今後も、「これは」と思った本があればまたまとめていきます。





